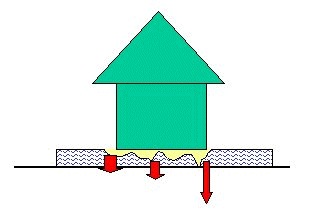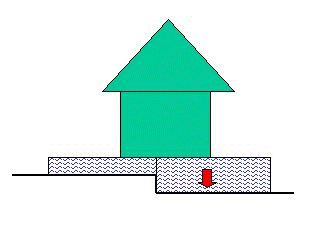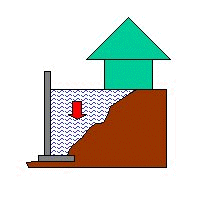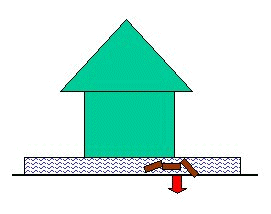こんな地盤は危ない
「圧密沈下」 造成地・宅地の多くは盛り土をしています。何年も経って落ち着いた
状態になるまでには、自重で締め固まって沈下します。また、土は重
いので、その下の地盤が軟弱な場合はその下が沈下したりもします。
宅地は転圧といって、人為的に締め固めをしますがそれが不十分な
場合、沈下します。これを圧密沈下といいます。
大抵、圧密沈下は不均等におこります。その為、上にのっている建物が
傾くのが不同沈下です。
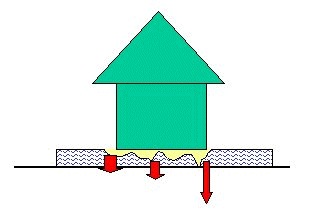 |
盛り土の転圧が足らないと、土は自重で沈む。 この圧密沈下は不均等におこることが多い。 |
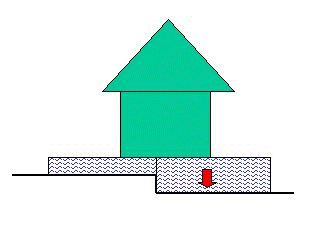 |
ひな段造成など切り土と盛り土が混在しているような場所、昔水路があった場合、など盛り土が不均等な場合は不均等に沈下する。(転圧不足の場合) |
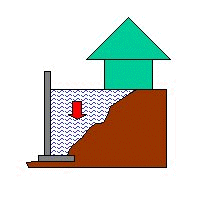 |
コンクリートの擁壁は、工事の時裏側をごっそり掘ってあり、のちに埋め戻します。その為、図のように固い所と柔らかい所があり、両方にまたがって家を建てると傾く可能性があります。 |
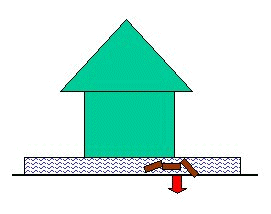 |
ひどい話ですが、埋め戻し土にガラ(建築廃材)をまぜて廃棄費をごまかす者がいます。当然、ガラが腐ったり、ガラの間に土が流れ込むと沈下します。建築廃材は、いまや環境問題の一番大きな部分です。廃棄費が妙に安い業者は、何かしら怪しいと思ってよいと思います。造成業者が埋める場合もあると聞くので注意が必要です。 |
他に・・・
・ 昔に 谷、くぼ地、水田、河川 だった場所 または そのような場所を宅地造成
した場所は軟弱である可能性が強い。
・ ベタ基礎は、通常は軟弱地盤に有効です。が、ベタ基礎は重いので時には
軟弱地盤に負担を与えて、下に固い・柔らかいがあると傾く原因になる事もある。
その場合は、ベタ基礎の根入れを深くして、土を排除する分の重みを(土そのもの
が重いのでそれを)取り除いてやるなどの工夫が必要。
自分でできる地盤チェック
・ 地名 昔からある名前をチェック。地形を名前にしてる場合がある。特に「水」に
からむ文字が入っている場合は要チェック。逆に山とか台とか丘(岡)など
は良い地盤の可能性あり。
(例)
|
地形の表現 |
水・川・谷・沢・河・池・沼・淵・瀬・江・久保(窪) |
|
水に密接なもの |
田・畑・井・堀・堤・船 |
|
水に住む動物 |
鶴・亀・貝・鷺・鴨 |
|
水辺の植物 |
蓮・荻・蒲・柳 |
・ 各種情報 インターネット (ジオテック等、リンクページ参照)、
地図 (古地図、等高線行政発行の防災地図等)、
地盤調査近隣データ
(市役所建築課構造係に行くとボーリング調査の
データを収集していて、地区ごとに幾つかづづファイルしてある。
見せてくれと言うと閲覧させてくれる。
場所が近く、地形が似ている所のデータが幾つか共通していれば、
目当ての土地もそのデータに似ている可能性が高い)
・ 周辺調査 周辺に水場はないか
暗渠となってる地下水路はないか-上は緑道になっていたりする。
不同沈下してる家はないか
-屋根の線が波うっていたり、窓・床下換気口
の隅から斜めにひびが走る。
・ 敷地を調べる 長さ1mくらいの鉄筋棒を用意して、敷地のあちこちに体重をかけて
刺してみる。柔らかいとズブズブ潜る。ガラが埋まっている場合は
10〜20cmくらいの深さなのでガリガリした手ごたえがあるときは
注意。
表面の水はけや柔らかさも注意。雨に日に行くとわかる場合もある。
スコップで20〜30cm掘ってみて柔らかかったり、水が出たりしたら
要注意。